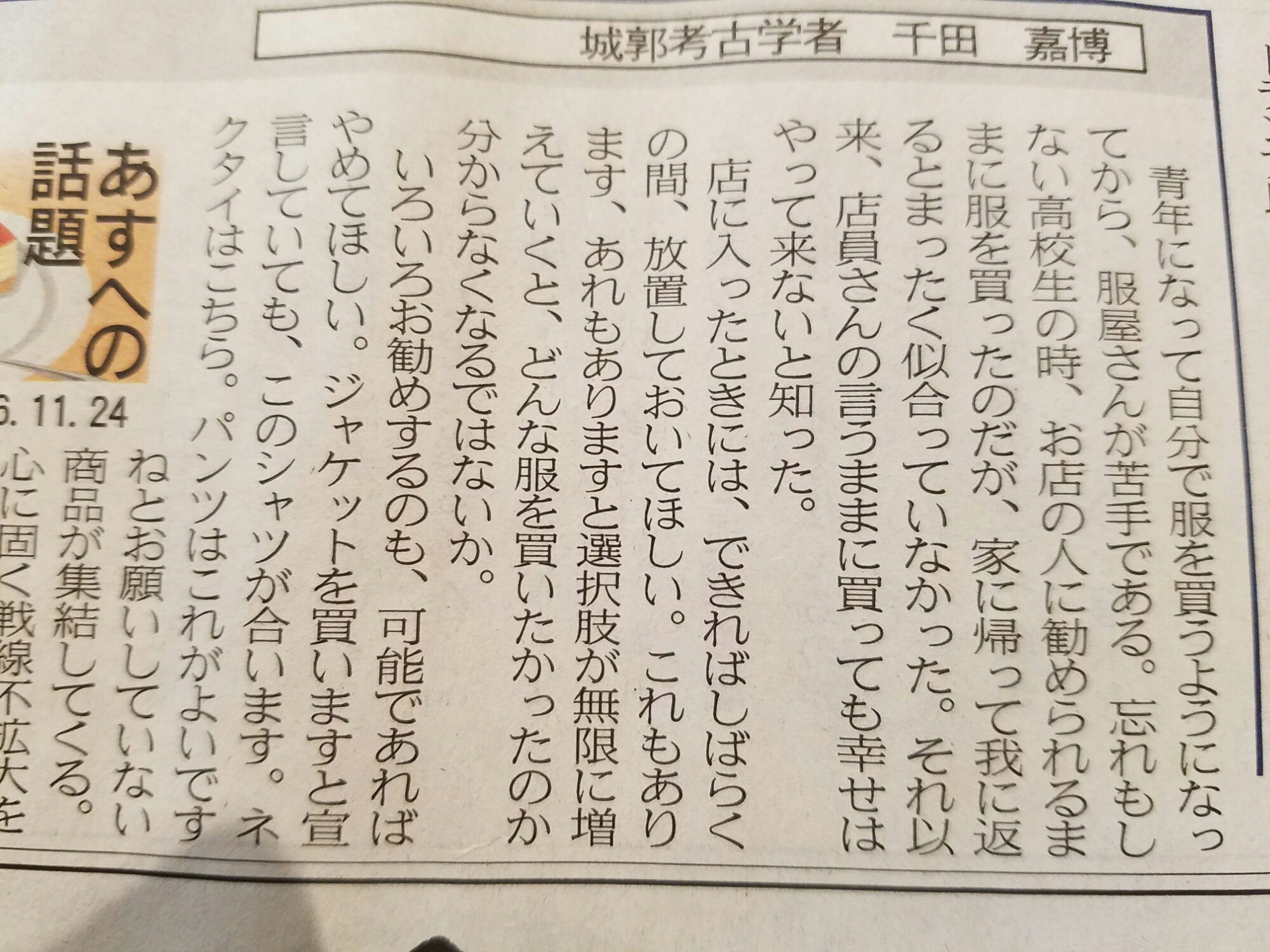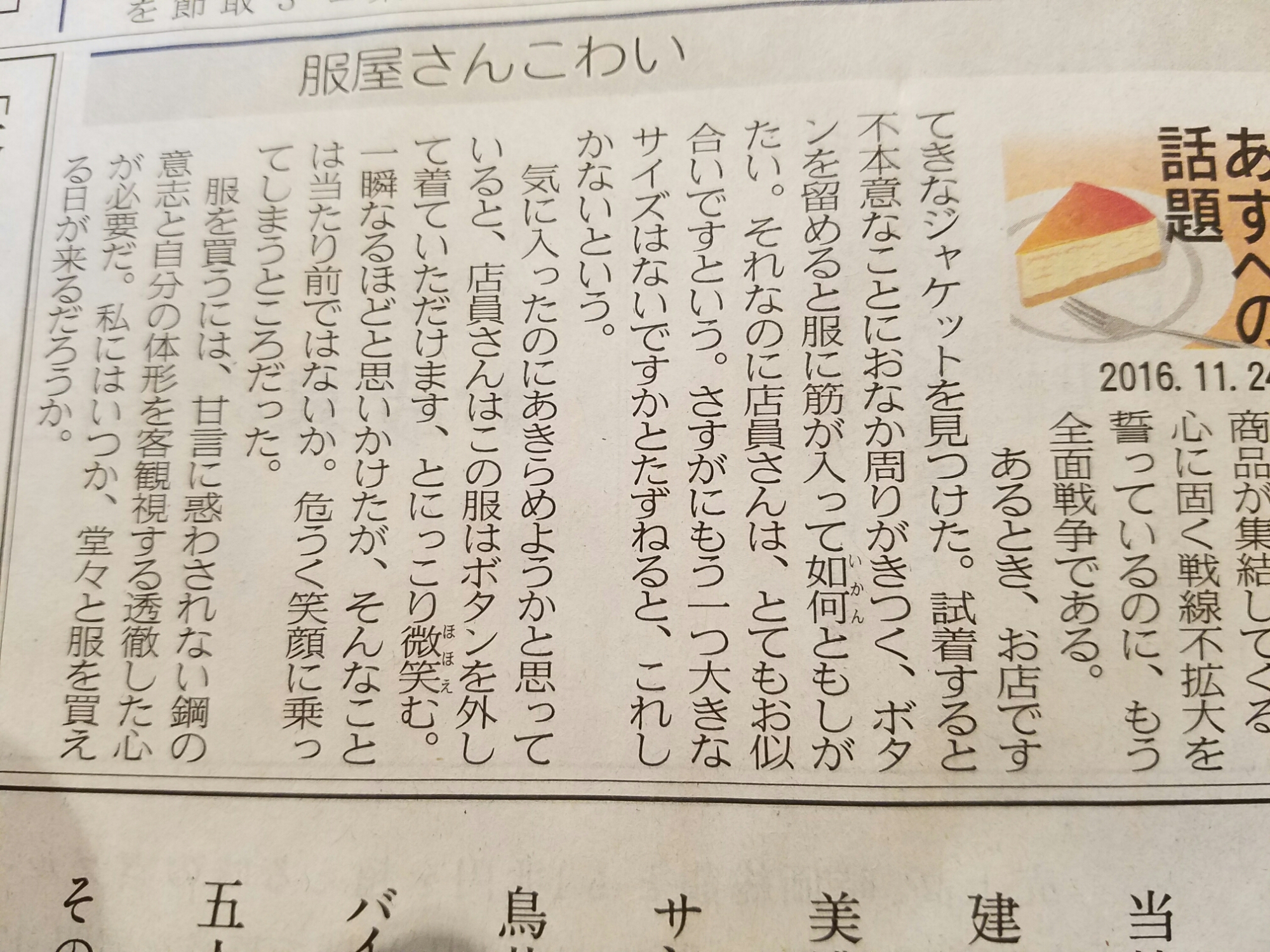販売員の教育
11月24日付け日経新聞夕刊のコ「あすへの話題」
非常に考えさせられる文章です。私が百貨店に入社した時の教育では、正にこのような接客を教わりました。当時の顧客は目まぐるしく変化する社会や生活に対しての溢れる情報に追い付いて行けず、その道のプロのアドバイスや情報に頼っていました。時代は進み、顧客は当時と比較にならない規模の情報に曝されており、やはりプロのアドバイスを求めています。当時と異なるのは、顧客がある程度自分の好みを自覚しており、流行に左右される事なく、ライフスタイルに関する情報を望んでいる点です。しかし、販売員の接客レベルは50年前なのです。多くの百貨店は 複雑化したポイント制度やレジ操作教育ばかりで肝心の接客方法は教えていないのが現実です。
今こそ顧客のニーズにきちっと対応できる販売員育成をするべきです。