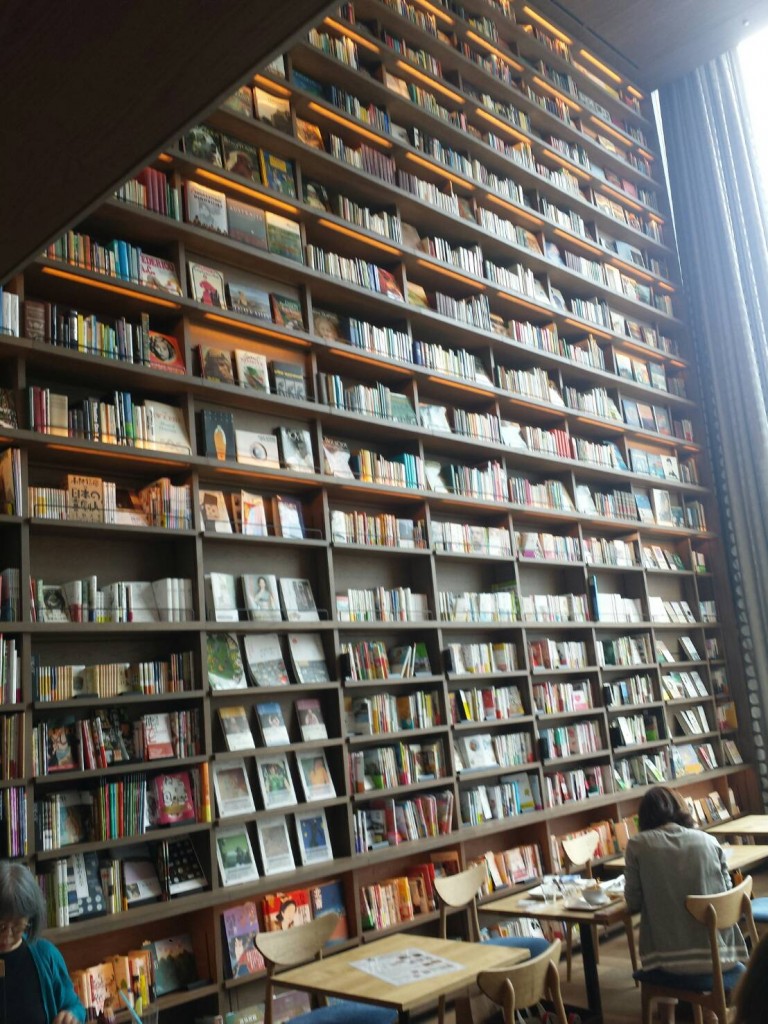伝統とは革新の継続
九谷焼錦山窯の吉田幸央氏と奥様るみこ氏の展覧会を拝見してきました。
伝統工芸というと、昔からの伝統技法をそのまま受け継ぐだけのモノが多い中で、技法をより昇華させ、素材を現代に求めた斬新かつ美しい作品展でした。
多くの窯が時代の流れの中に消えて行きましたが、百貨店や総合GMSと、相通じる原因があると思われます。それは伝統の上に胡座をかき、時代の求めるモノを認識出来なくなった事が最大の原因だと思います。どんな時代においても、必要とされなくなれば、どんなに素晴らしい商品でも、消えざるを得ません。
吉田先生達の作品は、伝統に甘んじることなく、常に革新を続け、伝統の刷新する鼓動が聴こえてくるようです。
どんな業種業態でも、革新を続けなければ生き残れはしないのです。